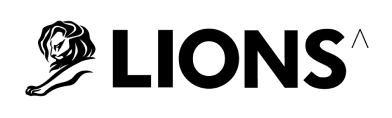コロナ禍においてWWFは2022年10月に『Living Planet Report 2022』を発表しています。このレポートでは自然と生物多様性の健全性を測る数値が過去約50年間で69%減少していることを報告しています。こういった地球規模での「環境課題の解決」にはコミュニケーションのチカラが常に求められています。コミュニケーションの課題として感じるのは、科学的知見やデータに基づいた少し複雑な情報を多くの方々にどう適切に伝えていくか、ということ。環境課題は、多くのアクターや多くのステークホルダーが関わりますが、関係する人の数が増えるほど、それぞれの視点や思惑での言動や状況が絡み合ってきます。また、システム思考に代表されるように、複雑な環境課題は一つのシステムとして捉え、俯瞰(ふかん)した視点でアプローチしなければ、一つの部分最適での解決が結局は別の部分に課題を生み出してしまい、全体最適化に至ることができないという負のループに陥りがちです。そしてその説明においても複雑で難しいから“一言では言えない”となってしまうと、コミュニケーションにおいても、誰かに話す際にちゅうちょが生まれたり、正確を期すため根拠を盛り込み過ぎることで長文になってしまうなどもよくあります。情報の送り手の多様な意図、情報の受け取り手の多様な状況、この間を正確さだけでなく、どう“適切”につなぐか、ここに神経を注いでいます。
これらの課題に取り組むとき、まずわれわれが大切にしているのは「Theory of Change」といわれる社会課題解決の手法です。状況を俯瞰して見るため、ステークホルダーマッピングといわれる手法で、その環境課題にいったいどのような人たちが関わっているのかを書き出し、関係性を図示化していきます。つぎに直接ヒアリングすること。関わっている人たちがどんな状況で何を考えていて何をしたいと思うのか、そのインサイトを探るのです。そしてその後の具体的な戦略づくりでは、レバレッジポイントはどこか、ボトルネックはどこか、情報の送り手と受け手がエンゲージするポイントはどこかを研ぎ澄ましていきます。最後に工夫を凝らすのがクリエイティブジャンプです。このプロセスを行ったり来たりしながら、もしくはプロトタイプをまずは実行し、コミュニケーション施策を徐々に更新しながら進めていきます。このようなステップを踏みながら、よくある一般的で曖昧な言葉で放置せず、解像度を高めていきます。
次の段階では、「SAVE NATURE PLEASE」というWWFが推進している環境保全のための行動変容フレームワークを用います(https://www.wwf.or.jp/campaign/snp/)。前述のロジカルな解像度と同様、またはそれ以上に重要視しているのがエグゼキューションで、その施策が笑顔をつくれるか、深く感動させられるか、誰かに話したくなるかなど、最終的なアウトプットの表現クオリティーの管理が、伝わる伝わらないを大きく左右すると考えています。WWFが注目しているのは、行動科学に基づく人々の意識変化や行動変容です。環境課題は人々の意識や行動によって発生する一方で、解決することができるのもまた人々の意識や行動によります。フレームワークの中に「NATURE」の六つの頭文字を集めたエグゼキューションで考慮すべき行動原則があるのですが、例えば「Normal」では人は所属するコミュニティーでの社会的アイデンティティーが肝要であり、そのコミュニティー内での規範化を進めるために相互支援を行い行動の拡散を行うということ。例えば「Rewarding」では人はインセンティブとディスインセンティブに影響されがちであり、損失回避をするためには積極的に行動するということなど、多くのTIPSや成功事例に当てはめながら、表現技術をブラッシュアップしています。
こういった指針やフレームワークに加えて、誰と仕事をするのかも今後ますます重要になってくると思います。より大きな社会的インパクトを生み出すには、NGO/NPOも組織内部だけのリソースにとどまらず、共感いただける外部との協働が不可欠でしょう。部分最適に陥らずに、全体最適を考えられるクリエイティブな協力者を見つけ出さなくてはいけません。逆にそういった方々にも自分たちを見つけていただき、関心を持っていただけるように、われわれが何を考えていて何をしたいのかの発信は常にアップデートしていきたいと考えています。
このような方針に基づき、WWFジャパンが近年取り組んでいるのが、ペットとして利用され絶滅の危機にさらされる野生動物をゼロにするキャンペーンです(https://www.wwf.or.jp/campaign/uranokao)。野生動物のペット飼育についての意識調査を行った結果、絶滅や密猟や密輸などのリスクがあることをよく知らないという回答が68%もありました。これらのリスクがある野生動物を飼いたいという層を対象に、動物園の飼育員さんが野生の生態や習性など飼育の困難さやリスクを解説する動画を作成、拡散によって意識変容を目指す活動を始めたばかりですが、どんなにかわいくてもペットに適さない動物がいることを知ってほしいですし、その投げかけには多くの賛同の声が寄せられています。